<アフィリエイトリンク>
こちら、長くて読みにくいのですが、とても良い本でした。はじめは著者自身(アメリカの白人かつ知的に高いASD)の話が続いたので「本を買って失敗したかな」と思ったのですが、読み進めていくうちにそれは間違いだったことに気付きました。とてもおすすめの本です。
おすすめ度
おすすめ度…★★★★★
読みやすさ…★★☆☆☆
対象…発達特性を持つ当事者や、その家族に特におすすめです。
定型発達者の社会で仮面をつけ、マスキングして生きてきた著者
著者のデヴォン・プライスは社会心理学者、博士、大学助教授でありASD(自閉スペクトラム症)の当事者。いわゆる高機能ASDです。彼はこれまでずっと定型発達者の社会に合わせて「仮面」をつけて「マスキング」して生きてきました。
この「マスキング」には、ASD者が定型発達者に溶け込むために行う「擬態」と、ASDによる困難やを穴埋めするために特定の戦略をとる「補償」があるそうです。
著者はこの「仮面」と「マスキング」によって、機能が高く自立しているという見せかけを維持することで、定型発達者の社会で認められて生活をしてきました。
仮面をつける日々に限界がくる
しかし著者は「仮面」をつけて生活すること、「マスキング」して定型発達者のようにふるまうことに限界を感じてしまいます。身体はボロボロになっていました。
感覚過敏である一方感覚刺激を求める
著者は常に色々な音にイライラさせられる一方で、そのノイズを打ち消すほど強烈ではっきりした感覚を求めていました。つまり感覚過敏である一方、感覚刺激を求めていたのです。
感覚刺激を求めるASDの場合、大音量の音楽、スパイシーな食べ物、明るい色、大量の活動、動きを強く欲することがあるそうです。
(感想)確かにおともスパイシーな食べ物が好きだし、激しく動くことが好きです。
ASD者に見られるいろんな特徴
また、著者によるとASD者には以下のような特徴もよく見られるとのことです。
・声の大きさを調整するのが苦手
・腕や手をバタバタさせるのが好き
・感覚刺激を求める一方で身体的な痛みには比較的無感覚
・刺激で気が散りやすい一方、楽しいと感じる活動に固執しすぎてトイレや食事を忘れて何時間も熱中する過集中傾向がある
・アルコールやカルト教団に依存しやすい
著者自身も、社会不安と感覚過敏の問題を抱えてきて、それを麻痺させるためにアルコールに依存してきたそうです。
(感想)おとも、感覚刺激を求めていつも手をパタパタさせてます。そしてLaQやプラモデルなどの微細運動を、時間を忘れて没頭しています。感覚刺激を求める一方で身体的痛みに無頓着であるという点も、おとに当てはまります。
「高機能」という概念
「機能している」という概念そのものが、資本主義の理論とプロテスタント由来の労働理論を前提にしており、そのどちらも生産性がその人の価値を決めると信じるように私たちを仕向けてきた。働いて価値を生み出すことができない障害者ほど、この世界観に傷つけられてきた者はいないだろう。
「自閉スペクトラム症の人たちが生きる新しい世界」デヴォン・プライス より引用
(感想)知的に遅れがないASD者は「高機能ASD」と表現されますが、じゃあ知的な遅れがあると「低機能」なのか?「機能」とは脳の機能について指しているのか?
私は以前からずっと「高機能」という表現を不思議に思っていましたが、本のこの一文を読んですごくしっくりきました。
生産性がその人の価値を決める現代社会においては、障害などによってその価値を生み出せない人ほど「低機能」とみなされてきたし、ずっと傷つけられてきたんだな…と。
療育は、定型発達児に近づける訓練なのか
筆者によると、「ABA(応用行動分析)療法による療育は、ASD特性を隠すように子どもたちを導き、いわば定型発達児らしく振舞う訓練」であるとのことです。
(感想)おとが通っていた療育の多くもABAに基づいており、「今後の社会で生きやすいように」という目標のもと療育が行われていました。それは深読みすれば「定型発達者の世界で生きやすいように」という意味であり、「定型発達者に近づける訓練」という側面もあったと思います。それは当時から感じてはいました。
ただおとが通っていた療育においては、本書に書いてあるABA療育のような過激な罰は全く行われていなかったし、先生方も本気でおとのこの先の未来を考えてくださっていました。
確かに、生産性を重視した社会が少しずつ変わっていくべきであるとは思うのですが、現状そういうわけにはいかない。それにおとが通っていた療育は、定型発達者に近づける訓練ばかりというわけでもありませんでした。療育によって「出来た」という経験が増え、それがおとの自信に繋がったのもまた事実です。
自分に気を配る
著者は障害をカミングアウトし、同じ特性を持つ人や信頼できる友人たちと交流し、本来の自分を取り戻していきます。仮面をとりはじめるにつれ、他人の反応を警戒することをやめ、自分の身体や気持ちを尊重できるようになっていきました。
著者によると、ASD者は自分の体に気を配ったり、自分の欲求を認識して主張することに苦労する場合が多いため、それを意識して気を付けることが重要だとのことです。
・感覚刺激を求める自分を癒す。マッサージローラーなど。
・感覚過敏のセルフケアをする。ノイズキャンセリングイヤホンの使用、刺激の少ない楽な服を着る、物による刺激を減らしたミニマルな部屋づくりなど。
・社会において成人が子どもっぽくて幼稚なものに対して興味があるという事自体嫌悪されがちであるが、自分の好きな物を好きでいる。
・特別な興味を掘り下げる時間を持つことで、元気が回復する。
著者が望むことは、ASDを持つ人たちが、本当の自分の姿をなるべく恥じることなくすごせるような社会だそうです。
感想、懺悔
おとが年中~年長時代の2年間、私はおとに色々詰め込み、無理をさせていたように思います。当時私は「小学校入学までに、定型発達の社会でなるべくおとの困りごとが少なくなるよう、今訓練しなければ。」と必死になっていました。愚かでした。
おとは知的障害を伴うASD児なのに。それは変えられないのに。
「定型発達が社会の基準」「定型発達に少しでも近づけるべき」という私の勝手な願いの元、療育やOT、ST、さらに栄養療法や感覚統合訓練やクリニックの言語レッスンなど、私はおとに多くのことを強いていました。
おとが当時これらをどう思っていたのかは詳しくはわかりません。なぜならおとは言葉でそれを説明できなかったので。いつもひたむきに頑張り、ニコニコと私に笑いかけていただけでした。
私は本当に愚かでした。さらに自分に対しても無理を強いてしまい、結局私は精神を病んでしまいました。
転勤帯同で都会から自然が豊かな地方に転居し、おとが小学校に入学し、幸運にも個々のペースを尊重してくださる特別支援学級担任の先生に出会い、私はようやく気づきました。
「ああ…小学校の先生って、こんなに寛容だったのか。」と。
私は一気に肩の力が抜けました。と同時に、おとに対して申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
「ASDだから、知的障害があるから、できないことはできない。おとはおとらしくいればいい。」ずっと頭ではわかっていたものの、そんな簡単なことを、やっと心で受け入れることができました。
それ以降、私はおとに何か無理をさせることはやめました。私も(おそらくおとも)、本当に楽になりました。
この本の中で、著者は置かれた環境や知能の高さから自己を偽り、定型発達者の仮面をつけて長年無理をし続け、それが限界に達する過程が描かれていますが、それがどんなに苦しかったことだろう…と心が締め付けられました。
おとにはそんな無理はしてほしくない。それを再認識したと同時に、定型発達者の社会になるべく適応させるため、おとに無理をさせようとしていたかつての自分にゾッとしました。
改めて、今後もおとは自分に合った環境で自分らしく生きていってほしい。その手助けをするのが私の役目だと思っています。適度な距離を保ちつつ…これからも親子で生きていこうと思います。
~終わり~
<アフィリエイトリンク>

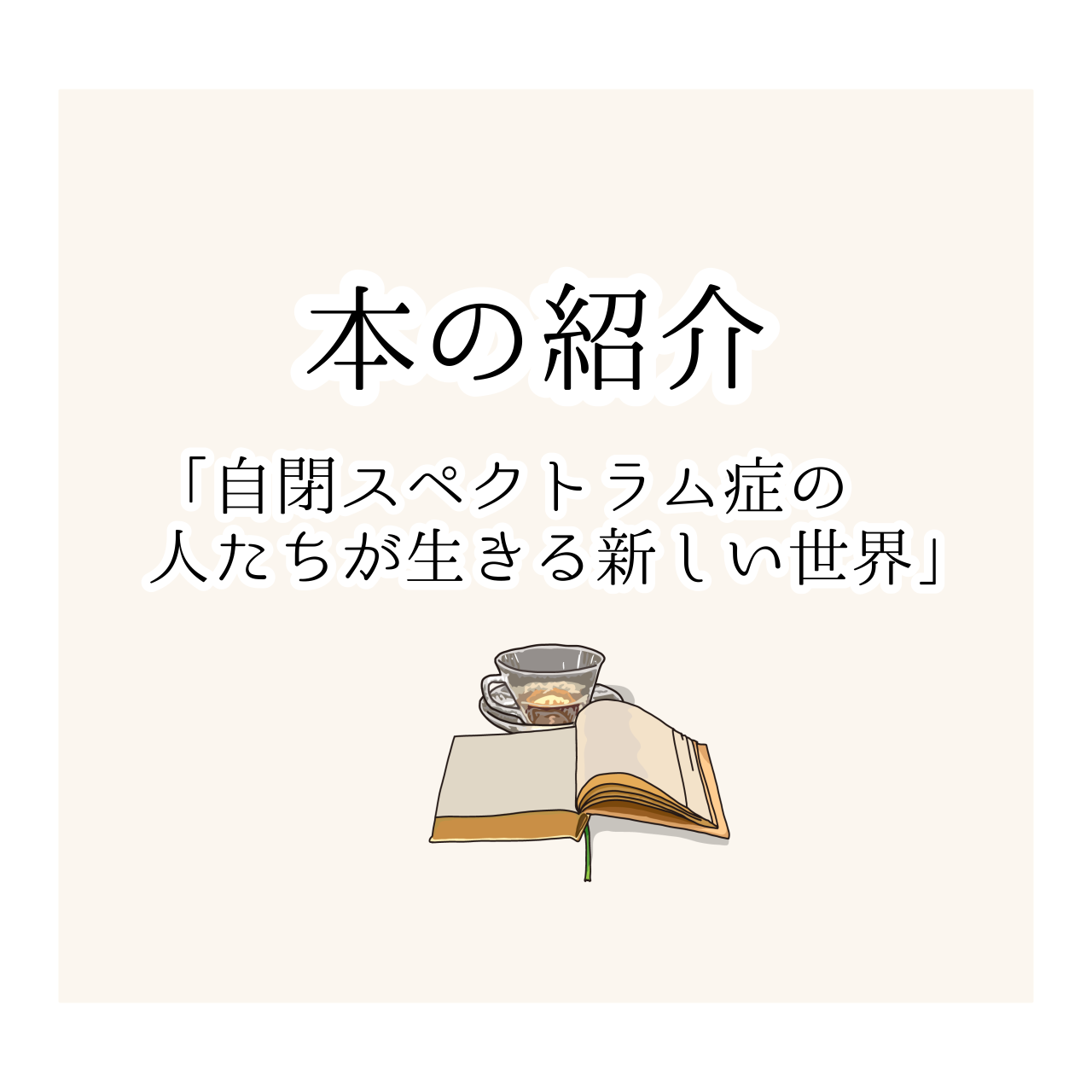

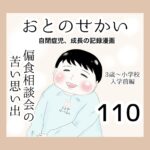
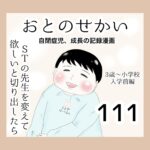
コメント
感覚刺激!目からウロコでした
うちも大音量で音楽を鳴らし、やめてと言っても聞かず辛い食べ物を好み、自分の痛みには無頓着
当てはまる…
今日は朝からお弁当のおかずを捨てられ、ディに行く前に泥の中でわざと転び、ディからはお友達やスタッフを叩くという散々な日でしたがブログを読んで少しだけ心が落ち着きました
ひろこさん、ブログへのコメントありがとうございます!
こんな長文を読んでいただきありがとうございます( ;∀;)
大変な一日でしたね。きっとひろこさんが日々向き合われていることが、お子さんの成長につながっていると思います✨
息子も当てはまることが多いのですが、「感覚過敏だけど感覚刺激を求めてしまう」という理由を当事者の方から聞くとしっくりきますよね…!